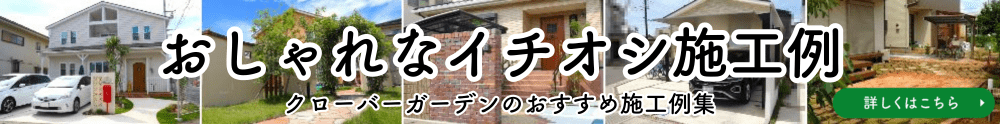ヤマボウシはおすすめ庭木【常緑の種類もシンボルツリーに最適!】
【更新日】2025.09.03.

庭を彩るためにヤマボウシを選ぶかどうか、多くの人の悩みの種になっています。その選択に迷い、不安を感じているあなたに向けて、この記事が明確な解答を提供。ヤマボウシは本当に庭にふさわしいのでしょうか?その疑問を解消するために、詳細なリサーチと専門家の意見をもとに解説を進めていきます。
ヤマボウシの選択を考えるとき、その美しい花や管理のしやすさが大きなメリットです。しかし、どのようにしてその美しさを最大限に引き出し、健康的に育てるかが鍵となります。この記事では、栽培方法や剪定のテクニック、さらには種類ごとの特性まで、具体的な方法を解説するつもりです。
この記事を読み終えるころには、ヤマボウシを庭木として選ぶことの大きな利点と、それを美しく保つためのノウハウが手に入ります。不安を感じていたあなたも、これからは自信を持ってヤマボウシの管理ができるようになるでしょう😊

このページの目次

当社クローバーガーデンは、埼玉県で営業する「外構と庭工事の専門会社」です。年間60件ほどの工事を行い、今までたくさんのお客さまにご満足いただきました。
わたしたちは、施工とデザインにおいて高い専門知識と技術を持ち、お客さまの理想とする家づくりをお手伝いしています。家の外まわりならすべて工事でき、庭木の植栽や芝張りまで幅広く対応できる業者です。
ヤマボウシってどんな木なの?
落葉中高木樹のヤマボウシは、日本を含めた東アジア原産です。
もともとは、寺院や山で植えられる程度でした。しかし昭和40年以降、桜のすぐ後に花を咲かせるハナミズキに人気が出始めると、相乗効果でやまぼうしにも人気が集まるようになりました。
現在では庭の主役になれる樹木として、里山にある雑木の雰囲気をだす庭木の代表格になっています。
- 【分類】落葉中高木
- 【学名】Cornus kousa
- 【漢字】山法師
- 【別名】ヤマグルマ
- 【科名】ミズキ科
- 【属名】ミズキ属
- 【原産地】本州~九州、朝鮮半島、中国
- 【花言葉】返礼、友情
1本立ち種と株立ち種があり、狭い庭には、株立ち種をおすすめします。広い庭なら、ヒメシャラ・シマトネリコ・アオダモと組み合わせると良いでしょう。
名前の由来は?
ヤマボウシ(山法師)の花の中心にある丸いつぼみの集まりを「法師の坊主頭」に、白い総苞を「頭巾」に見立てたことに由来しています。
花言葉はなに?
「返礼」「友情」など良い意味があります。
【5つ】庭木×シンボルツリーにおすすめな理由 ⭐
ここからは、庭工事歴20年以上の現役プロが、ヤマボウシの魅力をたっぷり解説していきます。
ヤマボウシには常緑樹と落葉樹があり、どちらも人気のシンボルツリーです。
目隠しや日除けにしたいなら常緑ヤマボウシ、秋の風情を感じたいなら落葉ヤマボウシを選びましょう!
1.【人気シンボルツリー】株立ちなら成長速度が遅い
- シンボルツリーの中でもとくにオススメ!
- 初心者でも育てやすい丈夫な庭木
- 自然に樹形が整い剪定もかんたん!
シンボルツリーの中でもとくにオススメ!
ヤマボウシはシンボルツリーとしておすすめの庭木です(とくに株立ち)。
2018年に当社クローバーガーデンで植えたシンボルツリーを集計したところ、ヤマボウシをいちばん多く植えていました。人気がある理由は、お客さまの満足度が高くクレームも少ないからです。
- 【樹高】10~15m
- 【葉張り(樹冠の横幅)】10~15m
- 【花色】白、ピンク
- 【開花期】5~7月
- 【果実色】赤
- 【果実熟期】9~10月
- 【用途】シンボルツリー、庭木
ヤマボウシは樹高10~15mほどになる落葉中高木樹で、日本自生種であるため育てやすい庭木です。里山の趣を持つのが魅力で、日本人好みの庭木といえます(和風・洋風どちらもOK!)。
上画像の外構×庭工事での植栽例はこちらです⏬
アートウッドデザインの高級エクステリア工事【おしゃれな門まわり施工例です】
初心者でも育てやすい丈夫な庭木
ヤマボウシは庭木初心者でも育てやすい庭木です。
ヤマボウシは日本自生種なので、日本の気候風土にとても合います。つまり、虫がつきにくく枯れる心配が少ない庭木なので、目立つ場所に植えるシンボルツリーにおすすめです。
狭い庭やベランダでも楽しめる
ヤマボウシのほとんどの品種が鉢植えでも育ち、成長速度が遅いので扱いやすいです。
樹高1mぐらいまでは6号鉢、1.5~1.7mぐらいで10~12号鉢で育てらます。ただし、限られた用土の量なので十分肥培し、2~3年おきに植え替える必要があります。
また、大きなワイン樽を2つに切った大型コンテナなら2m内外の木が植えられるので、根元に横に広がる草花やユキヤナギ、コトネアスターなどをあしらうと立派なミニガーデンができます。
自然に樹形が整い剪定もかんたん!
ヤマボウシは放任しても自然に樹形が整うので、広い庭に植えればあまり剪定は必要ありません。
ただ、狭い場所で育てる場合は、適切な枝抜き剪定をすることで、無用な枝の伸びが抑えられます。手つかずの自然を、身近に感じられる樹形が魅力です。
2.【常緑ヤマボウシの種類もある】落葉との見分け方は?
- 常緑ヤマボウシの種類もある
- 落葉ヤマボウシの種類・品種
- 常緑と落葉との見分け方は?
常緑ヤマボウシの種類もある
ヤマボウシは一般的に落葉樹ですが、中国原産のヤマボウシには1年中葉をつける常緑樹の種類もあります。
たとえば以下の品種。
- 【ホンコンエンシス「月光」】小花で開花量が多い品種
- 【ホンコンエンシス「雪帽子」】矮性種の小型品種
- 【マウンテンムーン】ブータンで発見された品種
- 【ヒマラヤヤマボウシ】黄色がかった花色品種
- 【ウィンターレッドペイジ】花色品種
- 【リトルルビー】八重の花色品種
落葉ヤマボウシより、花のあでやかさは欠けるのがデメリット。ただし花径が5~6cmと小輪ですが花つきがとてもよく、秋口に真っ赤な果実をたくさんつけるメリットがあります。
常緑樹は「日陰を作る」「目隠しにする」といった目的に使いやすく、玄関前やリビング前に植えるといいでしょう。
落葉ヤマボウシの種類・品種
落葉ヤマボウシのほうが常緑樹より品種が多く、たとえば以下の品種があります。
- 【ミス・サトミ】濃いピンク色の総苞片を持つ
- 【ベニバナヤマボウシ】総苞片が淡紅色の華やかな品種
- 【ミルキーウェイ】普通種よりも花つきがよい
- 【ビッグアップル】果実が大きな品種
- 【ウルフアイ】白覆輪の斑入りの品種
- 【ホワイト・ミヌマ】普通種よりも花つきがよい
- 【ゴールドスター】葉の中心に黄色の斑が入る
- 【紅富士】びっしりと花を咲かせる品種
- 【筑波の峰】白花を咲かせる品種
落葉樹のデメリットは、やっぱり落ち葉の掃除がめんどくさいこと!住宅街で隣家と近いなら、落葉期の掃除はこまめにやらないといけません。
メリットは冬には葉が落ちて、あたたかい陽光が差し込む庭になること。夏は常緑ヤマボウシ同様、葉っぱが厳しい日差しを遮ってくれます。
常緑と落葉との見分け方は?
見分け方は以下です。
- 常緑は一年中緑で、落葉は冬は枝だけ
- 紅葉は落葉樹のほうが赤色が強い
- 常緑の葉は厚く緑色が濃い
常緑ヤマボウシは寒さに弱いので、北関東以北だと冬に枯死する可能性があります。南関東だと、冬に半分ぐらい落葉するでしょう。
冬の寒さの厳しい地域なら「落葉ヤマボウシ」の一択。それほどでもなければ、「常緑・落葉どちらでも」元気に育ってくれるでしょう。
3.【美しい花】ハナミズキとの違い+おすすめはどっち?
- 小ぶりで清楚な白い美しい花が咲く
- ライバル「ハナミズキ」との違いは?
- あなたにおすすめなのはどっちかな?
小ぶりで清楚な白い美しい花が咲く
ヤマボウシの開花期は5~7月と長く、白くて繊細な花を咲かせます。
ヤマボウシで白く見えるのは、本当は花ではなく総苞片(そうほうへん)というものです。花は総苞片の中心に20~30個の集まりあまり目立ちません。
ただ、総苞片も合わせて花と見れば、ハナミズキより小ぶりで清楚な花がとてもきれいです。総苞片は先端がとがった端正な表情で4枚からなり、ヤマボウシの樹冠を埋めるように咲きます。
とくに花つきがよい品種は、満開時に花の重みで枝がしなるほどです。紅花の種類(ベニバナヤマボウシなど)は、よく日に当たる場所に置くときれいに発色してくれます。
ライバル「ハナミズキ」との違いは?
ヤマボウシはハナミズキと同属で、似ていることが多いです。
しかし、ヤマボウシが庭木で人気が出てきたのは最近で、一般住宅ではまだわずかに植えられている程度です。それに比べ近縁種のハナミズキは、全国どこででも見られるほど普及しています。
ヤマボウシがハナミズキほど多く見られないのは、ヤマボウシは花が5~7月と少し間をおいて開花し、花のあでやかさに欠け、品種が少ないなどの理由からです。
ただ、最近のはやっている庭木テーマは「雑木風」なので、ヤマボウシの人気が急上昇しているのも当然の結果と言えるでしょう。
花はものすごく似ている
ヤマボウシに似た花はハナミズキで、どちらも美しく魅力があります。
ヤマボウシは総苞片(そうほうへん)にくぼみがなく先端がとがっていて、ハナミズキは先端にくぼみがあるのが違いです。
ヤマボウシの方が全体的にすっきりした印象を与え、新緑が美しい5~6月に登山に出掛けると真っ白な花が目に飛び込んできます。園芸品種のベニフジやミスサトミなどは、ピンク色のかわいらしい花を咲かせます。
まとめると以下です。
| ヤマボウシ | ハナミズキ | |
|---|---|---|
| 花の特徴 | 先端がとがる | 先端がくぼむ |
| 開花時期 | 5~7月 | 4月 |
| 果実 | 赤くて大きい | 赤くて小さい |
| 食べられる? | OK | NG |
| 印象 | すっきりした雑木 | 華やかな花木 |
| 病気・害虫 | ほとんどない | よく発生する |
参考にどうぞ!
あなたにおすすめなのはどっちかな?
選び方のポイントは以下です。
- 【ヤマボウシ】雑木の雰囲気が好き
- 【ハナミズキ】華やかな雰囲気が好き
どちらも育てやすい庭木なので、いっぱい悩んでから決めましょう!正直言って、どっちも正解です。
また、和風の庭があり「どうしてもハナミズキを植えたい!」って人は、代わりにヤマボウシを植えましょう。
ハナミズキの詳細はこちらです⏬
ハナミズキはシンボルツリーや庭木におすすめ【デメリットは派手すぎることかな?】
4.【食べられる赤い実がなる】ジャムや果実酒にしよう!
ヤマボウシの実は生でも食べられ、マンゴーやバナナ、アケビの味に似ていてとてもおいしいです!(ちょっと薄味だけど...)
花後に結実する果実は8月下旬~10月に赤く熟し、どろんとした甘さで中には種子があります。時期はちょうど学校の夏休みが終わる頃です。
たとえば、以下のように食べられます。
- 生食
- ジャム
- 果実酒
- ドライフルーツ
見た目が「悪魔の実」のようですが毒はなく、生でもおいしく食べられますよ。
ヤマボウシで作るジャムのレシピ
- ヤマボウシの果実:100g
- 砂糖:20g
- レモン汁:味を見ながら加える
まず皮をむきしっかり水洗いします。砂糖を加えて鍋で弱火で加熱し、木ベラで潰しながら煮て、沸騰したら火からおろしてこします。
もう一度火にかけ、とろみが出るまで煮詰めます(ここで味を見ながらレモン汁を加える)→完成!
※煮詰め過ぎないのがポイントです!
ヤマボウシで作る果実酒のレシピ
- ヤマボウシの果実:1kg
- ホワイトリカー(焼酎)35%:1.8l
- 氷砂糖:100~200g
- レモン:1個
ヤマボウシの果実の皮はむかずにしっかり水洗いしたら、水分はよく拭き取り、陰干しするなどして水気を取ります。
果実酒用の容器に入れ、ホワイトリカー・氷砂糖・レモンを加え、2~3ヶ月漬け込みます→完成!
※長期保存(2年以上)する場合は、保存性を良くするために漬け込み時に35%ホワイトリカーを少し多めに入れましょう。
※ブランデーを使うのもオススメです!(大人な感じ)
5.【秋の紅葉が美しい】うまく紅葉しない人にアドバイス
ヤマボウシの秋の紅葉は風情がありとっても美しい!
葉が明るい赤色から黒っぽい赤色まで、1枚1枚違って見えるのが特徴です。里山にある雑木の雰囲気が味わえるので、なんだか懐かしい気持ちにさせてくれます。
うまく紅葉しない人にアドバイス3つ
ヤマボウシを上手に紅葉させるポイントは、以下の3つです。
- 日当たりが良い場所
- 昼と夜の温度差が大きい場所
- しっかりした管理(剪定作業も)
やっぱり日当たりはいちばん大事です!1年を通して葉に日が当たる場所を選び、日陰になる場所には植えないでください。
また、昼夜の温度差が必要なので、建物から離れた場所に植えると良いです。住宅地では車の排気ガスにも注意してください。
もちろん、基本的な植木の管理・手入れは必要です。あとで解説するので、そちらを参考にどうぞ!
【剪定の仕方】剪定時期やおしゃれな樹形にする方法
- 最適な剪定時期はいつ?
- 自然樹形を生かすとおしゃれになる!
- 芯止めすると高さを抑えられる
- 小さくコンパクトに維持する剪定とは?
- 剪定だけしてくれる業者ってあるの?
最適な剪定時期はいつ?
剪定の基本は以下です。
- 【剪定の適期】12~2月(落葉樹)、6~7月(常緑樹)
- 【仕立て方法】自然樹形
剪定適期は落葉樹は12~2月、常緑樹は6~7月(花が咲き終わった直後)です。
自然樹形を生かすとおしゃれになる!
ヤマボウシは放任しても自然に樹形が整うので、特に剪定は必要ありません。
狭い場所で育てる場合は、場所に合った大きさで楽しむ必要があります。基本は樹冠を一斉に刈り込むことはせず、枝抜きをして自然樹形に保つことです。
芯止めすると高さを抑えられる
ヤマボウシを低く仕立てたいとき(芯止め)は、目的の高さの輪生枝の上で切ります。これはハナミズキと同じように、枝を輪生状に発生させるからです
枝張りの制限については、樹冠周囲の枝を切り取り、切る枝はつけ根から切るようにします。
また、太い幹や枝を切った時は、切り口に保護剤を塗っておくと、枯れる心配が少なくなるので忘れずに!
小さくコンパクトに維持する剪定とは?
庭植えのヤマボウシは適切な枝抜き剪定をすることで、無用な枝の伸びが抑えられます。
鉢植えは矮性品種を選び、7~10号ぐらいの鉢で育てるのがおすすめです。
ヤマボウシはハナミズキなどと同様に枝葉の出方が対生(たいせい:幹の同じ部分から両側方向に枝が出ていること)で、放っておくとかんぬき枝や車枝となりやすいです。若木のうちに樹勢を見ながら、交互に枝を間引いて基本樹形に整えることを意識しましょう!
【育て方のコツ】花が咲かない人はこれを実践しよう!
- 知っておくべきヤマボウシの基本情報
- 植付け・移植(植え替え)
- 水やりのコツ
- 肥料のじょうずなやり方
- 増やし方(実生・つぎ木・挿し木)
- 枯れるのを防ぐ病気・害虫の対策と薬剤
知っておくべきヤマボウシの基本情報
- 【植栽適地】本州、九州、四国
- 【成長速度】★★☆ 普通
- 【日照】★★☆ 日なた~半日陰
- 【土壌の質】砂壌土
- 【土壌の乾湿】★★☆ 普通
- 【根の深さ】★★★ 深い
- 【耐寒性】★★★ 強い
- 【耐陰性】★★☆ 普通
植付け・移植(植え替え)
「落葉樹は2~3中旬」、「常緑樹は4~6月と9月」が植え付けや移植の適期。
庭土が砂質や粘土質の土の場合は堆肥や腐葉土を少し多めに入れて、保湿性のある肥沃で水はけのよい土が理想です。
植えつけ場所は、日当たりのよいところから午前中日が入るところがよいでしょう。特にヤマボウシの園芸品種「ミス・サトミ」や「ベニフジ」などのように紅花種は、日当たりのよいところのほうが発色がキレイに出ます。半日陰でも育ちますが、開花量が少なくなり、秋の紅葉も鮮やかさにかけてしまいます。
ヤマボウシは少し高めに植えつけ、根を乾かさないように根元に敷きわらなどのマルチングをすることがポイント!切り詰めではなく、枝抜きによって樹形を整えてから植えます。
水やりのコツ
庭植えは夏期に晴天が続き、ひどく乾燥している場合を除き必要ありません。
鉢植えは鉢土の表面が乾いたらたっぷり与え、冬期は控えめにしましょう。
肥料のじょうずなやり方
庭植えの場合は、普通の庭土であればあまり必要ありませんが、寒肥(2~3月頃)として油かすと骨粉を等量混合したものを根元に施すといいでしょう。
鉢植えの場合は、寒肥は固形の緩効性化成肥料や有機質肥料を置肥するのが簡単で、初夏と初秋に化成肥料などを施しましょう。
増やし方(実生・つぎ木・挿し木)
自生するヤマボウシは実生でふやします。
サトミやミルキーウェイなどの園芸品種はつぎ木(2~3月が適期)か挿し木(2~3月と6~8月が適期)でふやします。
実生のポイント
実生(みしょう)とは、種子から苗木を育てることです。
園芸品種以外のヤマボウシは実生でふやしますが、デメリットとして個体差が出るので、秋の紅葉の美しさが左右されます。
9~10月に採取した果実を茶色くなるまで乾燥させ、殻ごと手でもみほぐして中の種子を取り出します。1つの殻に5~6個の米粒大の種子が入っています。
植木鉢に赤玉土を入れ種子をばらまき、その上に薄く土をかけます。その後、表面の土が流れないよう、植木鉢の底面から土に水をしみ込ませる「底面給水」をします。直射日光を避け、半日陰で管理しましょう。
つぎ木のポイント
つぎ木のメリットは、親木と同じ性質を受け継ぐ樹木を作れることです。
ヤマボウシ園芸品種はつぎ木でふやし、適期は2~3月です。
つぎ木の方法は、つぎ穂(ふやしたい品種)と台木(だいぎ)の形成層を密着させ、つぎ木専用テープで固定します。形成層同士を隙間なく密着させるのがポイントで、木を切るナイフの切れ味が活着の良し悪しを決定します。
つぎ木後は半日陰に置き、水やりをしながら育てます。うまく活着したらテープを取り外し、つぎ穂の芽を1つ残し、その他の芽(台木とつぎ穂の両方)は切ってしまいます。支柱を立てて補助しておくと、活着部分が折れる心配がありません。
挿し木のポイント
挿し木のメリットは、親木と同じ性質を受け継ぐ樹木を作れることです。
挿し木の適期は、2~3月(前年の枝を使う)と6~8月(春の枝を使う)ごろです。
充実した元気の良い枝を選び、葉を数枚残し10cmくらいの長さに切り挿し穂を作ります。切り口は斜めにし、水を入れたコップに数時間つけ水あげします。これは発根を促す目的があります。
植木鉢に鹿沼土を入れ、挿し穂を半分ぐらいの深さまでさします。直射日光を避け、半日陰で管理しましょう。
枯れるのを防ぐ病気・害虫の対策と薬剤
ヤマボウシには病気や害虫がほとんどありませんが、日当たりと風通しが悪いと病害虫が発生します。
夏に幹の地際にテッポウムシが食い入ることがあり、葉にはイラガの幼虫による被害が見られることがあります。殺虫剤で駆除しましょう。また、うどんこ病はあまり発生しません。
【おすすめ5種類】通販で買えるヤマボウシの木
どんなヤマボウシを選んだらいいのか、まったくわからない...おすすめを教えてください!
ここからは、通販で買えるおすすめヤマボウシの苗木商品の紹介です。
値段相場は¥3,000~25,000ぐらい(大きさによる)で、やや高級な植木に分類されます。背の高さは1~2.5mほどで、小さい木は鉢植えに、大きい木はシンボルツリーとして使うことをオススメします。
植木を植えた経験がある方なら自分で植えるもよし、初心者なら植木だけ購入して業者に依頼してもよし。業者に依頼したら、その後の手入れの仕方もこっそり教えてもらいましょう。
1.落葉ヤマボウシ 株立ち
価格:¥~25,000
樹高:~2.0m
おすすめ度:5.0★★★★★
当社でよく植えるヤマボウシの株立ちで、玄関前のシンボルツリーとして使うとおしゃれに決まります。
日本の気候風土に合う庭木で、風通しと日当たりの良い場所に植えれば病害虫の被害が少ないです。落葉樹なので秋には鮮やかな紅葉が楽しめます。
2.常緑ヤマボウシ 株立ち
価格:¥~25,000
樹高:~2.5m
おすすめ度:5.0★★★★★
常緑樹のヤマボウシで、最近非常に人気のある品種です。1年中青々していて葉が落ちません。
花は小さいですが大量に花をつけ、真っ赤な果実もたくさんなります。目隠しに利用するのがオススメです!
2.落葉ヤマボウシ ウルフアイ
価格:¥3,000~
樹高:0.5~m
おすすめ度:4.0★★★★☆
白い縁が外側に入るヤマボウシの品種ウルフアイです。
涼しげで柔らかい印象の葉を持ち、明るい雰囲気の庭をつくってくれます。ちょっと変わったシンボルツリーを植えたいなら、このウルフアイがおすすめです!
4.落葉ヤマボウシ ミスサトミ
価格:~¥13,000
樹高:~1.5m
おすすめ度:3.0★★★☆☆
薄いピンク色の花を咲かせるヤマボウシ「サトミ」で、庭のアクセントになるシンボルツリーとして植えられます。
同じような品種に「紅富士」がありますが、サトミのほうが丸みのある花びらで色が薄いです。日によく当てることで、きれいに発色します。
以前に普通種を植えたことがある人、赤い花が咲く庭木を植えたい人にオススメです!
5.常緑ヤマボウシ 斑入り
価格:¥~40,000
樹高:~2.0m
おすすめ度:4.0★★★★☆
白い縁が外側に入る常緑ヤマボウシの斑入り品種です。
まだ新しい品種で、値段が高いのがデメリット。涼しげで柔らかい印象の葉を持ち、明るい雰囲気の庭をつくってくれます。
まとめ
この記事では、ヤマボウシの特徴や育て方(剪定・挿し木など)、庭木におすすめの品種も紹介しました。いかがだったでしょうか?
ヤマボウシは日本の気候風土に合うので、シンボルツリーとして手間がかかりません。9月ごろに熟す果実では「ジャムや果実酒」が作れ、秋の風情ある紅葉も楽しめるなど、ヤマボウシにはたくさんの魅力があります。
ヤマボウシは雑木の雰囲気を持つ庭木です。
ナチュラルガーデンに植える人も多く、玄関前のシンボルツリーにもぴったりですよ!
すぐ下の関連ページで「シンボルツリーランキング・ハナミズキ・ジューンベリー」を解説したページリンクを貼っておきます。
興味のある方はぜひご覧になってください😊
このページを読んだ人はこちらもオススメ!
以上、ヤマボウシはおすすめ庭木【常緑の種類もシンボルツリーに最適!】…という話題でした。
更新:2025年09月03日|公開:2023年03月18日